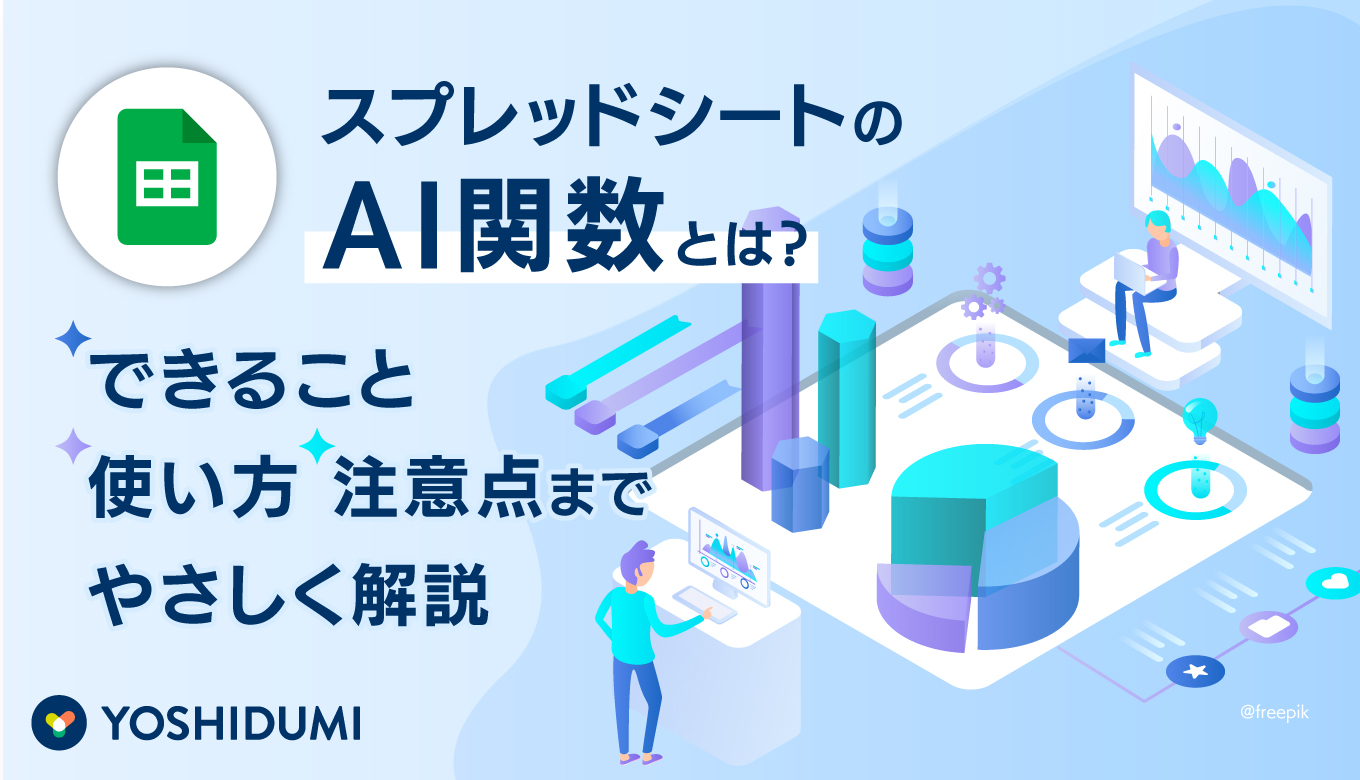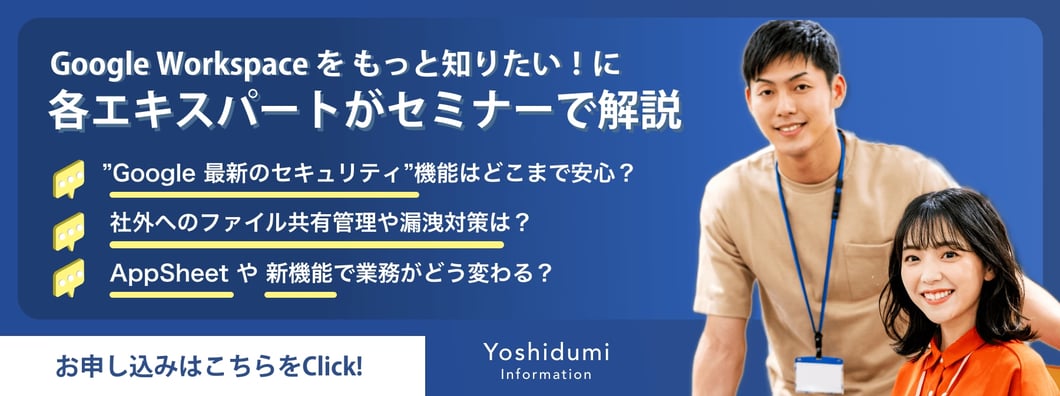Geminiが拓く新しい働き方:Workspace最新機能と活用例
絶えず変動する市場、激しい競争の中で求められるさらなる対応速度。どうすれば一歩先を行き、継続的に新たな価値を生み出すことができるのか。この問いに対する答えのひとつとして、「Gemini」を統合したGoogle Workspaceが挙げられました。全世界で月に20億回以上利用されているこの機能は、これまで膨大な時間を要した手作業を効率化し、従業員一人ひとりにとっての「強力な右腕」となります。
その具体的な活用例として、Google Workspace事業本部の部長である佐瀬 郁恵氏が登壇し、架空の食品会社「Cymbal Foods」の社員が、役員からの「健康志向とサステナビリティをテーマにした新商品の企画を翌朝までに」という高難度の緊急ミッションに、Geminiを活用して応えるというデモが披露されました。
1. リサーチ業務を数分で完了させる「Deep Research」
社員はまず、GeminiアプリのDeep Research機能を使い、Web上の情報収集に加え、Googleドライブから関連する社内文書をソースとして追加します。そして「市場における消費者トレンドを予測し、特定の観点でまとめて」と指示するだけで、Geminiが分析を開始してくれます。従来は膨大な時間を要したリサーチが、生産計画の提示まで含めて数分で完了し、レポートを作成することができました。このレポートは、Googleドキュメントに出力することができるため、チームでの共有も容易に行うことができます。
関連記事:Deep Researchの使い方で情報収集が変わる!活用ポイントと料金も紹介
2. 非構造化データを知識に変える「NotebookLM」
次に、企画の信頼性を高めるため、データソースを限定した専門的な分析に「NotebookLM」を活用します。過去の企画書や業界レポート、さらには会議の音声データといった、形式の異なる情報をソースとしてアップロードすることができます。NotebookLMはこれらの非構造化データを構造化して理解し、「具体的な凡例は?」といった簡単な質問を入力するだけで、必要な知見のみを引き出し、信頼性のある企画の作成を支援します。
関連記事:【必見】NotebookLMの活用事例&メリットをわかりやすく紹介!
NotebookLM導入ガイド:無料で資料ダウンロードする
3. データ分析を瞬時に可視化する「AI関数」
企画のヒントを得るため、消費者の声を分析するとしましょう。Googleスプレッドシートに参照したいSNS上のコメントを貼り付け、AI関数*に「テキストから読み取れる感情を分析し、ポジティブなものなら緑、ネガティブなものなら赤に色分けして」と指示するだけで、Geminiが瞬時にコメントを分析し、感情を視覚的に理解できるよう色分けしてくれます。
* AI関数について、Googleは多言語対応を順次進めていますが、Gemini in Sheetsの高度な機能(「Help me organize」など)は、依然として英語でのプロンプトが最も安定して動作します。他言語での利用も可能になってきてはいますが、機能が制限されたり、意図通りに動作しなかったりする場合があるため、英語での利用を推奨します。
関連記事:スプレッドシートのAI関数とは?できること・使い方・注意点までやさしく解説
4. 定型業務から解放する「Flows」
最後に、日々の情報収集を自動化するため「Flows」を使用します。特定のリストやメールアドレスなどからのメール受信をトリガーとしてワークフローを開始し、その次にすべきアクションを設定することで、業務の自動化がされます。また、Flowsの1ステップとして、受信したメールの内容をGeminiやGemを用いて要約・加工などをすることも可能となっています。
作成された情報は、社内の特定の共有ドキュメントに自動で蓄積するなど、Google Workspaceの各アプリと連携することでさまざまな活用ができるようになります。これにより、従業員はルーチンワークから解放され、より創造的な業務に集中できるようになるのです。この「Flows」は、すでに一部の顧客への提供が開始されており、今後、順次展開が予定されています。
今後の展開が楽しみですね!
関連記事:Google Workspace Flows発表! AIエージェントが日常業務を自動化、生産性の未来を変える
導入事例に学ぶ「AIとの働き方」
札幌市:16,000人規模の働き方改革
札幌市は、行政サービスの高度化を目指す「第二次ICT活用戦略」の一環として、デジタルワーク環境の刷新に着手しました。 登壇したデジタル戦略推進局 情報システム部長の小澤 秀弘氏は、背景にあった課題として、ライセンスコストの増大、組織間の情報共有の欠如、そして「最新版の資料が分からない」といった資料管理の破綻を挙げました。
なぜGoogle Workspaceか
同市がGoogle Workspaceを選んだ決め手は、単なるコスト削減やツール置き換えに留まらない「働き方そのものの変革」への期待と、ゼロトラストを基本とする強固なセキュリティ基盤でした。 「安全な土台があったからこそ、クラウド活用に一歩踏み出せた」と小澤氏は語ります。
導入後のハイライト
2025年5月から原則として全職員16,000人へ展開を開始。 その結果、早くも多くの職員の働き方に変化が現れています。
①組織の壁の解消
従来は部や課ごとの縦割りで分断されがちだった業務が、Google Workspaceではプロジェクトを軸にスペースに集まり、協業するスタイルへ変化。 これにより、意思決定のスピードが向上しました。
➁会議の質の変革
会議は「集まること」から「創造すること」が目的に変わりました。 アジェンダや論点を事前に共有し、会議が始まったら全員でドキュメントに書き込んでいくスタイルが定着。 資料データをNotebookLMに読み込ませて数分で高精度な議事録を作成したり、Geminiで蓄積データから課題や傾向を発見したりといった活用が進んでいます。 結果として、会議時間は平均60分から30分に半減し、一度の会議で結論に至るケースも増えました。
小澤氏は、「Googleは単なるプロダクトではなく、未来の働き方そのものを提供してくれた」と述べ、職員が内側から自律的に変わり始めている変革の手応えを語りました。
これらの事例は、Google Workspace with Geminiが個人の生産性向上のための単なるツールに留まらず、組織全体のナレッジ活用、意思決定の迅速化、そして創造的な働き方へと変化させる強力なプラットフォームであることを証明しているといえるでしょう。
まとめ
本記事ではGoogle Workspaceに関連した情報を記載しました。
基調講演で示されたのは、Google Workspaceが単なるツールではなく、組織の生産性を飛躍的に高める「生成AI民主化のプラットフォーム」であるという点です。従業員一人ひとりをルーチンワークから解放し、誰もが自律的に、より創造的な活動へ集中できる環境を提供する。これこそが、Googleのソリューションがもたらす「未来の働き方」であり、変化の激しい時代を勝ち抜くための新たな答えと言えるのではないでしょうか。




%20(1).png?width=1080&height=227&name=YOSHIDUMI_01%20(3)%20(1).png)